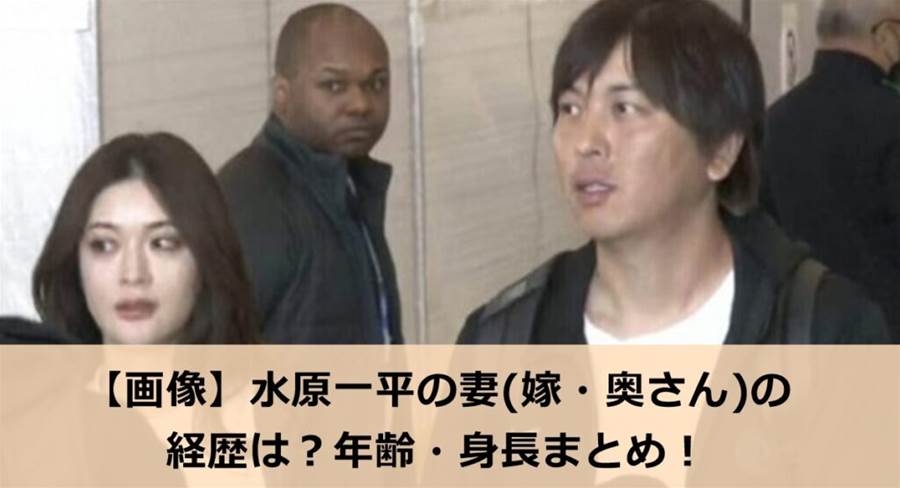航一が突然家庭裁判所に左遷されるところから始まります。これまでエリートコースを歩んできた彼にとって、この移動は明らかに不名誉なものでした。特に、彼の仲間である若手裁判官たちも同様の扱いを受けたことで、航一の胸には疑念と怒りが渦巻きます。
彼は、司法の独立が脅かされているのではないかという危機感を抱きつつ、長官の桂場(カラバ)に直談判します。しかし、桂場から返ってきたのは、理想論を捨て、現実に従わざるを得ないという厳しい現実でした。

「司法の独立を守るためには、時には犠牲も必要だ」と語る桂場の言葉に、航一は深い失望を感じます。これまで信じていた正義や理想が、大きな力の前に押し潰されていく様子を目の当たりにし、彼の心は大きく揺れ動きます。
物語の中盤、航一は米と轟木(とどろき)を訪れます。そこで、米から告げられたのは、「ありふれた悲劇」という言葉でした。
米は、存続殺人事件の被害者である美子(みこ)の母親が若い頃に家を出て、その後美子が母の代わりに虐待を受けるという、まさに悲劇的な人生を歩んできたことを語ります。「人間の所行とは言えないような事件だが、こうした悲劇は決して珍しいものではない」という米の言葉に、航一は衝撃を受けます。

この「ありふれた悲劇」というフレーズは、航一が直面する司法の現実、そして彼がこれまで信じていた理想と現実のギャップを象徴しています。航一は、世の中の不条理や理不尽な現実に対して、心を痛める暇はないと語る米に対し、自らの弱さと向き合わざるを得なくなります。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください